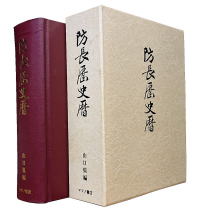
その月日にかけて詳述した格好の歴史読物
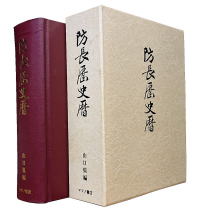 |
防長の政治・経済・教育・産業・文化など全般にわたる事歴一千項目余を網羅し、 その月日にかけて詳述した格好の歴史読物 |
| 防長歴史暦 | |
| 山口県 | |
| マツノ書店 復刻版 ※原本は昭和18年 | |
| 2001年刊行 A5判 上製 函入 1038頁 パンフレットPDF(内容見本あり) | |
| ※ 価格・在庫状況につきましてはHPよりご確認ください。 | |
| マツノ書店ホームページへ | |
| ■本書は昭和十一年に開始された「山口県史編纂事業」の初期段階で生まれた大著です。 ■史料の収集から始まり、本書の編纂に手間取っているうちに太平洋戦争に突入したため、肝心の『山口県史』は一冊も刊行されませんでした。 ■本書は枕頭の書として毎日読めるように作られていますが、入念な「索引」や「小年表」もついているため、「山口県郷土事典」あるいは「防長人名事典」としても活用できる便利な本となっています。専門家の使用にも充分に耐える内容です。 |
便利な『山ロ県郷土辞典』 内田 伸 |
| 『防長歴史暦』は昭和十八年の刊行で、当時山口県史編纂委員であった小川五郎、御薗生翁甫、広永達夫、石川卓美四氏の執筆になる。昭和十一年は明治維新七十年に当ったので、維新の大業に関係の深い山口県は、その記念として山口県史の編纂を企てた。翌十二年に県史編纂所が開設され、前記四氏がその編纂委員となった。この四氏は知る人ぞ知る、それぞれ透徹した史眼の持主であるので、今まで書かれている防長史を綴り合わせて県史としてまとめるということではなくて、この際さらに県下の資料を探索して、それらを充分に使用し、全く新しい山口県史をつくろうという構想であった。現在山口県文書館に多量に蔵されている県史編纂所史料がその時の収集の資料であるという。 その史料の収集に多くの労力がさかれたためか、県史はすぐに本文執筆というわけにはいかなかったようである。昭和十六年四月に、NHK防府放送局が放送を開始したが、その放送局から県史編纂所に、山口県の歴史上の出来ごとを毎日放送したいから、今まで防長に関係のある日毎の歴史を調べて原稿にしてほしいという依頼があった。 それによって各スタッフが、それぞれ手分けをして執筆されたのであるが、一年間の放送の後、それを増補訂正して一本にまとめたものが本書である。 内容は県史編纂のために作られていた年表の中から重要なものを抽出し、月日に係けて暦日体に編成したものである。 その事項は古代から昭和十五年までに至り、挙げられた項目は一七〇〇余を数える。その一件一件の説明は、実に的確に明解にまとめられている。 大内義弘の「応永の乱」、大内盛見の「宇佐宮の造営」、江戸時代の「撫育局創設」、「伊能忠敬の防長測量」、また幕末の「相州警衛」、「池田屋の変」さらに現代の「開作の築立」、「市制の施行」などなど、私どもはその事件は知っていても、原資料は何にあるか、誰にもわかるように短くまとめるにはどうすればよいかということによくぶつかる。 その時私は座右のこの本を利用している。実にこの本は「山口県郷土辞典」というべきものである。 本書に載っている人物は付録の索引項目で見ると五三一人ある。防長の人物辞典としては『近世防長人名辞典』(吉田祥朔著)『防長人物誌』(近藤清石著)などの立派なものがあるが、この『防長歴史暦』には両書に載っていない人物がさらに一八三人ある。 その主なものに中世大内氏関係の高僧がある。その高僧は文化、政治に大きな影響を与えたのであるが、今まで彼らの手軽な伝記集はなかった。本書によってはじめて大内時代の高僧の行跡をよく知ることができる。 また他の人物辞典に載っている人物でも、たとえば「所郁太郎」の項を見ると、『近世防長人名辞典』は、いわゆる辞典風な書き方であるが、この『防長歴史暦』は物語風に書かれている。両書あわせ見る必要を感じるのである。 本書は今まで、暦日別に歴史事項を並べたものということで、山口県史研究者の中でもあまり注目されなかったようである。どうしたことか、昭和二十九年に発行された『防長史料文献解題』(第二集)にも本書は載っていない。しかしその内容を見ると、防長の重要な歴史上の出来ごとが網羅されており、その文章はたいへん的確で要を得ている。この本には付録冊子があって、それには月別日別の項目の外に、年代表、項目索引がある。この項目索引によって『防長歴史暦』は辞典として充分に利用できるというわけである。座右に置かれて、手軽な山口県歴史辞典としての御利用をおすすめする次第である。 (本書パンフレットより) |
山口県の歴史小事典 〜ドキュメンタリーとして読む『防長歴史暦』 作家 古川 薫 |
| 『防長歴史暦』は、戦争たけなわの昭和十八年に編纂された。当時の県知事が筆を執ったその序文は、やはり今のわれわれの耳になじまぬ文言が並べられているが、あの悲壮な緊張感のなかで、これを編纂する意欲の底に敷かれているのは、時代を超えた歴史の存在感である。そして粛々とつづられた先人たちの動きは、如何なる時代、情況をもつらぬく価値を持ちつづけるのだ。 『防長歴史暦』は、日記体をとって防長の歴史を編纂したもので、同一年月日に生起した事件・事象を集めている。大内・毛利の戦国から、幕末長州藩の事項まで、重層的に記述されるので、幅広い時間枠のなかで、さまざまな人間の行動を俯瞰することもできる。 日記体で書かれた歴史を追うのは、通史を通読するのとちがって、臨場感のようなものがただようということもある。 たとえば「六月」は日本書紀の昔から昭和二年まで八十七の頃目で埋められているが、そのうち慶応二年「四境の役」関連の項目を拾うと以下のようである。 六月 七日 四境の役、大島口開戦。 六月十三日 長藩幕軍に応戦、書を遺る。 六月十四日 四境の役、芸州口小瀬川の開戦。 六月十六日 四境の役、石州口開戦。 六月十七日 四境の役、小倉口開戦。四境の役、益田攻略。 六月十八日 奇兵隊、小倉領田ノ浦占領。 (以下略) もちろん各項目には千字前後の解説があり、そのときの情況をドキュメンタリーとしてつかむことができる。九百二十頁に約二千項目が収められている。大著『毛利元就卿伝』など三卿伝を監修した渡辺世祐博士を顧間に、旧制山口高校教授小川五郎氏をはじめ御薗生翁甫・広永達夫・石川卓美の各氏が編纂委員となった。郷土史の泰斗が精査した内容にも信頼でき索引がついているので山口県の歴史小事典として利用できるのもありがたい。 『防長歴史暦』は、発刊当時、NHK防府放送局からラジオ放送されて評判になり、その後昭和五十年に歴史図書社によって復刻されたが、すでに古書店からも姿を消してしまっている。二十六年ぶりの復刻である。原本は戦時中のことで、製本も粗雑だが、マツノ書店の手で堅牢美麗な本としてよみがえるのが嬉しい。 (本書パンフレットより一部抜萃) |